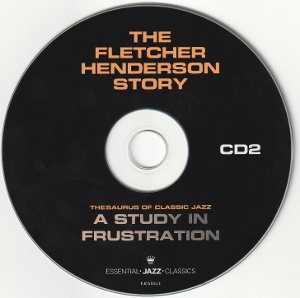「このフレッチャー・ヘンダーソンのバンドは、1930年の末に再び上昇の機運を迎える。この楽団にはコールマン・ホーキンス、ボビー・スターク、レックス・スチュワートだけが居残っていた(とシュラー氏は書くが、1929年のバンドとそれほどメンバーは変わらない)。トロンボーンには革新的なスタイルを奏するクロード・ジョーンズが加わった。しかし最も重要な変化はリズム・セクションにあったと言えるかもしれない。ドラムには、その長所と歴史的意義がジャズ史家たちに過小評価されてきたウォルター・ジョンソンであったし、ジョン・カービーも加わった」と。しかしジョン・カービー、ウォルター・ジョンソンが加わったのは1929年であり、その録音も前回取り上げている。
続けてシュラー氏は、「この楽団の新たな自信は、1930年の再結成後の最初の録音に反映されている」と書くが、この「再結成」がよく分からない。一度解散したのだろうか?氏は1928年と29年の間に重大な変更が発生したと書き、低迷期を迎えたと書くが「解散した」とは書いていない。「再結成」とは「低迷期」を脱出したという意味であろうか?
ともかく氏は続けて、「カーターはいくつかのまとまりのある編曲を提供したが、これは後年のスイングのスタイルを先取りしたものである」と高く評価している。1929年ではボロクソに言っていたが、1年で素晴らしく成長したらしい。続けて「ガーシュイン作の”サムバディ・ラヴズ・ミー”や”キープ・ア・ソング・イン・ユア・ソウル”は、リズム・セクションの4ビートへの転向を明示するもので、カービーのベースの足取りが軽快である。面白いことに、前者の場合、リズム・セクションは、ホーン楽器群がまだ対処できないやり方で、スイングしているのだが、2か月後の”キープ・ア・ソング・イン・ユア・ソウル”では、リズムの基本的な志向がホーン楽器群にも理解されるようになっている。この非凡な演奏について賞賛すべき点は多々ある。というのは”ヘンダーソン・スタイル”の最終的な秘訣が初めて明快な確信を込めて提示されているからである。カーターが、長い(?)試行錯誤の過程を経て、セクションをスイングさせる解決策をとうとう探り当てたことは明らかである」と。
そして次からが難しいことを述べる。「この解答は、シンコペーションにあった。サッチモやジェリー・ロール・モートンのようなモダンな奏者たちはリズム上の自由を獲得するカギが1小節4ビート(2ビートではない)に基づくシンコペーションにあることを本能的に察知していた。奏者がいったん4ビートを明示する役割を離れて、ビートの「内部」に入り込むことができるとすれば、リズムを自由に扱える膨大な地平が見えてくる。多分、ソロイストたちは、リズム・セクションが4/4ビートを扱えるまで待たなくてはならなかったのだ。ソロイストたちが4/4ビートを明示する負担から解放されたとき、彼らはさらに重要な課題に取り組めるようになった。その課題とは、多彩な旋律の提示であり、或いは多彩なリズムを用いてそうした旋律の事実上は自己批評となるものの提示である」と。正直僕には難しすぎてよく分からない。
 そしてシュラー氏は上記のことを理解してもらうために譜例を上げて解説している。
そしてシュラー氏は上記のことを理解してもらうために譜例を上げて解説している。「カーターは、”キープ・ア・ソング・イン・ユア・ソウル”の中で、この原理をセクションの書法に応用し、ヘンダーソンのレパートリーの偉大な編曲の一つを創り上げた。我々は、この曲の旋律を例に、ジャズのアンサンブルによって演奏されたある楽句が歳月の中でどのように変化したかを明らかにすることができる。
 1923年では、それは右上のように演奏されたであろう。そして1927年か1928年までには、右の真ん中のようにほぐされて演奏されたかもしれない。
1923年では、それは右上のように演奏されたであろう。そして1927年か1928年までには、右の真ん中のようにほぐされて演奏されたかもしれない。 しかし1930年のカーターの編曲では、この楽句は4ビートの箍(たが)から全面的に解放されて右下のように演奏される。
しかし1930年のカーターの編曲では、この楽句は4ビートの箍(たが)から全面的に解放されて右下のように演奏される。 シュラー氏は、右の3つの譜例を合奏で行われる場合を左の譜例で表している。その例としては同じ録音の後の方の、トランペットがリードする全セクションの演奏を上げている。この「同じ録音の後の方」とは、同録音はテイク1とテイク2があり、テイク2という意味だが、CDには片方しか収録されておらず、収録されているのがテイク1か2かの記載がない。
シュラー氏は、右の3つの譜例を合奏で行われる場合を左の譜例で表している。その例としては同じ録音の後の方の、トランペットがリードする全セクションの演奏を上げている。この「同じ録音の後の方」とは、同録音はテイク1とテイク2があり、テイク2という意味だが、CDには片方しか収録されておらず、収録されているのがテイク1か2かの記載がない。シュラー氏はさらにソロにも言及する。「”キープ・ア・ソング・イン・ユア・ソウル”には、3つの注目すべきソロ、それ自体としてもそうなのだが、時代を考慮すると一層注目に値するソロが含まれている。その3つとは、クロード・ジョーンズの大変モダンなビートを外したトロンボーン・ソロ(その背後のジョンソンの繊細で刺激的なシンバル奏法)、カーターのアルペジオが基本のフォーマットであるのに何とか巧みにスイングしているアルト・サックス・ソロ、そして最も驚異的なのが、最後のコーラスのブリッジにおけるスタークの短いトランペットソロである。」(譜例左下)
 シュラー氏は、次のように述べる。「またもや譜面ではその全貌を、とりわけ最初の数小節を伝えられないことになるのだが、これは1930年において、その15年後のディジー・ガレスピーとそっくりな響きをする個所である。この発言を信用していただくには聴いてもらうしかない。最後に付言すると、ジョー・スミスのリード・トランペットの輝かしい響き、高音のd音を含めてそのすべてに注目しなければならない。カービーの深々としたベース音とスミスの大きな音のリードによって、8声部の和声がジャズにおいて聴かれたことが無い次元を獲得しているからである」と。ここでシュラー氏は、Tp奏者をジョー・スミスと考えていることは明らかである。しかしCDの解説でも、Web版のディスコグラフィーでもTpはボビー・スタークとラッセル・スミスであり、コルネットにレックス・スチュワートということで一致している。Web版を見ているとどうもソロはレックスのような気もするが…。
シュラー氏は、次のように述べる。「またもや譜面ではその全貌を、とりわけ最初の数小節を伝えられないことになるのだが、これは1930年において、その15年後のディジー・ガレスピーとそっくりな響きをする個所である。この発言を信用していただくには聴いてもらうしかない。最後に付言すると、ジョー・スミスのリード・トランペットの輝かしい響き、高音のd音を含めてそのすべてに注目しなければならない。カービーの深々としたベース音とスミスの大きな音のリードによって、8声部の和声がジャズにおいて聴かれたことが無い次元を獲得しているからである」と。ここでシュラー氏は、Tp奏者をジョー・スミスと考えていることは明らかである。しかしCDの解説でも、Web版のディスコグラフィーでもTpはボビー・スタークとラッセル・スミスであり、コルネットにレックス・スチュワートということで一致している。Web版を見ているとどうもソロはレックスのような気もするが…。シュラー氏は、「チャイナタウン、マイ・チャイナタウン」にも触れ、次のように述べる。「1906年に作られた懐かしいスタンダード・ナンバーで、扇動的で興味深い演奏である。マッキニーズ・コットン・ピッカーズのアレンジャー兼Tp奏者ジョン・ネスビットが編曲したもので、テンポが四分音符=290というとてつもない速度に設定され、30年代前半としては全てのビッグ・バンドが身に付けた超人的技巧を披露するような類の曲であった。素早いサックスの動き、きびきびしたブラスのリフ、ホットで電光石火の速さの8分音符のソロ、容赦なく攻め込むリズムセクション(たった3分間で768のビートを刻む)、これらがその主要な成分であって、30年代の有名なビッグ・バンドはどれも、他のバンドとのカッティング・コンテスト(バンドの優劣を客の拍手で決めるバンド合戦)向けにこうした曲をレパートリーに持つ必要があった」と。