
いつでも厳しいガンサー・シュラー氏は次のように述べる。
「“West end blues”、“Muggles”、“Weather bird”、“Potato head blues”、“Beau koo Jack”のようなレコードは、ルイ・アームストロングの成熟した力を充分に表現したものだった。商業的な成功の圧力が今ほどに昔は強くはなかったとしても、これを越えてさらに成長することは、天才の彼ですらかなわぬ事であったろう。ルイがこうした商業的な制約によって全面的に屈服されなかったことが彼の偉大さを測る尺度である。彼は30年代を同世代の他の大半の人間よりも上手に生き延びたし、またこの時代を、例えば彼の師匠のキング・オリヴァーの20年代よりもはるかに巧みに生き延びられた。事実、アームストロングの天才の復元力はとてつもないもので、60歳を過ぎても演奏と歌唱力は技術的に損なわれなかった。長年の間、派手なスタンド・プレイをやり、大げさな演技をして道化役も務める芸人生活を送りながらも、彼の芸術は壊されなかった」と。
実際1930年は、大恐慌の影響で録音が激減したと言われるがルイ・アームストロングの録音はどう見ても減っているようには見えない。1929年ルイはキャロル・ディッカーソンを音楽監督して、自身がリーダーとなりニューヨークに進出、“コニーズ・イン”などに出演するとともに、翌30年初めまでオール黒人キャストによるレヴュー“ホット・チョコレート”に出演した。その直後ルイ・ラッセル楽団のゲストとしてワシントンD.C.に向かい、帰って来てからも自分のバンドやザ・ココナッツ・グローブ・オーケストラに加わって演奏するなどしている。さらに30年にはシカゴに戻ったり、初めてカリフォルニアに行き8か月間に渡り滞在したという。
このカリフォルニアでは、フランク・セバスチャンの経営する“ニュー・コットン・クラブ”に7月からソロイストとして出演した。当時このクラブに専属出演していたレオン・エルキンスのバンド(30年秋からレス・ハイトが率いる)と共演したが、そこにはローレンス・ブラウンやライオネル・ハンプトンが在団していた。
1930年のルイのレコーディングを見ていくと、5月まではニューヨークで行われ、7月からはカリフォルニアのロスアンゼルスで行われている。

| Band leader , Trumpet & Vocal | … | ルイ・アームストロング | Louis Armstrong | |||
| Trumpet | … | ヘンリー・レッド・アレン | Henry Red Allen | 、 | オーティス・ジョンソン | Otis Johnson |
| Trombone | … | J.C.ヒギンボッサム | J.C. Higginbotham | |||
| Clarinet & Alto sax | … | アルバート・ニコラス | Albert Nicholas | 、 | チャーリー・ホームズ | Charlie Homes |
| Clarinet & Tenor sax | … | テディ・ヒル | Teddy Hill | |||
| 3Violin | … | 不明 | Unknown | |||
| Piano | … | ルイ・ラッセル | Luis Russell | |||
| Guitar | … | ウィル・ジョンソン | Will Johnson | |||
| Bass | … | ポップス・フォスター | Pops Foster | |||
| Vibraphone | … | ポール・バーバリン | Paul Barbarin | |||
| Drums | … | バンド・ボーイ | The band's valet |
| CD4-17. | ソング・オブ・ザ・アイランド | Song of the island |
1930年最初の録音は、1月24日に行われた。前回1929年12月の録音との変更点は、ホーギー・カーマイケルが抜け、ヴァイオリン奏者が3人加わり、ポール・バーバリンはヴァイブラフォンのみ演奏し、ドラムはバンド・ボーイが叩いたという。
解説の大和明氏によると、1936年に本物のハワイアン・バンドを起用してデッカに採録したナンバーで、ここではハワイアン・バンドの代わりに、劇場オーケストラから3人の白人ヴァイオリン奏者を借りて冒頭に配するなど、かなりコマーシャルな線を狙っているという。ハワイアンのムードを出したいからといってヴァイオリンを入れるというのもよく分からないが、ドラムを叩いたバンド・ボーイといい不思議な人員配置ではある。
そもそも何故ハワイアン?と思わざるを得ないが、まぁ僕などが小さいころは、日本でも大スターと言われるような人は、「〇〇、ハワイアンに挑戦!」とか「カントリー・ウェスタンに挑戦!」、「時代劇に挑戦!」のような企画ものがあったような気がするので、多分それに近いものだったのかもしれない。或いはアメリカ本国でハワイ・ブームが起こっていたのかもしれない。それはそうと、この頃には「ハワイアン」という音楽スタイルが一般的に知られていたというのは興味深い。メロディーは確かに「ハワイアン」を思わせるものがある。
大和明氏は、こういった企画でもさすがにルイは立派なTpソロを披露していると追記している。ルイのヴォーカルはスキャットのみで歌詞はない。

| Drums | ⇒ | ポール・バーバリン | Paul Barbarin | |
| 3Violin | ⇒ | 抜ける | ||
| Clarinet & Alto sax | … | アルバート・ニコラス⇒ | ウィリアム・ブルー | William Blue |
| CD4-18. | ベッシー・クドント・ヘルプ・イット | Bessie couldn't help it |
| CD4-19. | ブルー・ターニング・グレイ・オーヴァー・ユー | Blue turning grey over you |
前録音の1週間後の録音。企画もので参加したヴァイオリンが当然のように抜け、バーバリンがドラムに戻る。クラリネットとアルト・サックスを担当していたアルバート・ニコラスが抜け、ウィリアム・ブルーが加わる。ウィリアム・ブルーはミズーリアンズのメンバーとして1929年の録音に参加している。
[ベッシー・クドント・ヘルプ・イット]
ルイ以外に短いが2か所あるヒギンボッサムの個性豊かな、おおらかで奔放なTbプレイも注目に値する。
[ブルー・ターニング・グレイ・オーヴァー・ユー]
僕にはそれがどこか分からないが、大和明氏は最初の1コーラスのルイのソロには一か所ミスがあるという。ちょっと変な音が入る箇所があるが録音の問題のような気がする。ともかくそのミスを帳消しにするだけの美しい繊細な味をたたえたミュート・プレイが素晴らしいとし、またヴォーカルの後に続くこれも大らかな味のあるTbソロを経て、今度はオープンで吹くルイのTpはエモーショナルで素晴らしいプレイだと思う。

1930年2月、ルイはニューヨークで根城としていた「コニーズ・イン」での契約を終えるとキャロル・ディッカーソン楽団を解散し、「ココナッツ・グローヴ」で働き始めた。ここのバンドはウィリー・リンチをリーダーとし、<ココナッツ・グローヴ・オーケストラ>と名乗っていた。ルイはこのバンドに加わると、4月には共にボルチモアへ巡業に出ている。なおこのバンドは1931年デューク・エリントン楽団のマネージャーを務めていたアーヴィング・ミルズがマネージャーになってから次第に売り出し、その名もミルズ・ブルー・リズム・バンドと名称を変え、ハーレムの実力バンドに変身していったという。
なぜルイはディッカーソンの楽団を解散し、ウィリー・リンチの楽団に入ったのかは記載がない。そしてレコーディングはたぶんボルチモア巡業へ出る前と思われる4月5日に行われたが、この日録音は2つのセッションに分かれる。
1つ目は、当時ピアノ、歌、ダンス、トランペットもこなし、“バック・アンド・バブルス”というチームで人気があった芸人のバック・ワシントンとのデュオで演奏した1曲。それと上記の<ココナッツ・グローヴ・オーケストラ>に加わっての2曲である。解説の通りだとすれば、ルイは既存のビッグ・バンドに客演したものであるが、バンド名は「ルイ・アームストロング・アンド・ヒズ・オーケストラ」となっており、その名称でレコード発売されたようだ。この経緯は僕の推測だが、やはり既にスターダムにのし上がりつつあったルイの名前を使った方がレコード販売に効果的という判断があったものと思われる。

| Trumpet & Speech | … | ルイ・アームストロング | Louis Armstrong |
| Piano | … | バック・ワシントン | Buck Washington |
| CD4-20. | ディア・オールド・サウスランド | Dear old southland |
この曲は、黒人霊歌の“ディープ・リヴァー”を下敷きとして書かれたものだという。このようにTpとPの対話のような演奏は極めて珍しいのではないだろうか?大和氏は、ルイは1928年ピアノのアール・ハインズとのデュオで見事なインタープレイを示したが、ここでもまた別の面で素晴らしいデュオ演奏を披露する。ハインズとのデュオは対等の音楽的交流という感じであったが、ここではルイがあくまでもリードし、時折セントルイス・ブルースの旋律を用いながら、心を込めてノスタルジックに吹いた名演である。

| Band leader , Trumpet & Vocal | … | ルイ・アームストロング | Louis Armstrong | |||
| Trumpet | … | エド・アンダーソン | Ed Anderson | |||
| Trombone | … | ヘンリー・ヒックス | Henry Hicks | |||
| Clarinet & Alto sax | … | ボビー・ホームズ | Bobby Homes | |||
| Alto sax | … | セオドア・マッコード | Theodore McCord | |||
| Clarinet & Tenor sax | … | キャスター・マッコード | Castor McCord | |||
| Piano | … | ジョー・ターナー | Joe Turner | 、 | バック・ワシントン | Buck Washington |
| Guitar | … | バーナード・アディソン | Bernard Addison | |||
| Tuba | … | ラヴァ―ト・ハッチンソン | Lavert Hutchinson | |||
| Drums | … | ウィリー・リンチ | Willie Lynch |
| CD4-21. | マイ・スィート | My sweet |
| CD4-22. | 恋とは思えない | I can’t believe that you’re in love with me |
パーソネルについて、上記はCDに付属の解説から拾ったもので、これは”The Chronogical Louis Armstrong 1930-1931”(Classics 547)記載のパーソネルと一致する。しかしちょっと<?>なのは、アルトのセオドア・マッコードとテナーのキャスター・マッコードである。上記のように書くと別人のはずであるが、Web等で検索すると”Theodore McCord”という人物は殆ど出てこず、”Castor McCord”を検索するとフルネーム”Theodore Castor McCord”という人物が登場する。アルトのセオドア・マッコードとテナーのキャスター・マッコードは同一人物であろうか?それなら別項を設けず、
Clarinet , Alto sax & Tenor sax … Theodore Castor McCord
と記載するはずである。それとも音の高い方ClとAsは”Theodore”で低い方のTsは”Castor”名義でプレイすることにしているのであろうか?どうにも分からん。
[マイ・スィート]
フランスの著名なジャズ評論家ユーグ・パナシェは、録音されたルイの演奏の中で最上のトランペット・ソロの一つかもしれぬと絶賛しているという。大和氏も確かに良い出来であると書いている。一方ガンサー・シュラー氏は、ルイはソロの高い方の音の音域をe♭まで広げた。素材がどんなに安っぽい曲であろうとも、彼の音は安定し、旧式な技術の録音でも白熱的な特質を帯びて煌めいている。当時彼の楽想は、型にはまり大半がホット・ファイヴ時代の反復であったが、確実に表現されたと誉めているのかいないのか分からぬ解説をしている。
なおこの曲だけピアノは2人で弾いている。僕にはヴァイブラフォンも入っているように聴こえるのだが、これはピアノの高音かもしれない。
[恋とは思えない]
ラスト・コーラスにおけるルイのソロも、パナシェ氏はもう一つの、素晴らしいソロだと称賛している。またルイのヴォーカルのバックを付けるバーナード・アディソンによる生ギターも実に美しいオブリガードを弾いているし、マッコードのテナー・ソロ、ヒックスのトロンボーン・ソロもいい味を出している。
さて、ルイは1か月後の5月に<ココナッツ・グローヴ・オーケストラ>との最後の吹込みを行う。CDも4枚目から5枚目に移る。ルイが加わった期間は実に短期間であるが、これはたまたまそうなったのかもともとそういう計画だったのかは分からない。
この時は4曲録音されたが、1曲目[インディアン・クレイドル・ソング](インディアンの子守歌)を除いてよく知られたスタンダード曲とディキシー・ナンバーが録音された。いなくなるのだから置き土産を置いていくということなのだろうか。
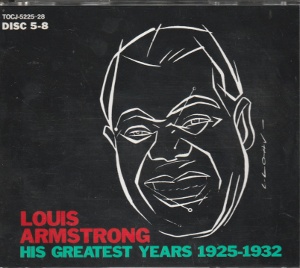
4月5日と同じメンバー。
| CD5-1. | インディアン・クレイドル・ソング | Indian cradle song |
| CD5-2. | イグザクトリー・ライク・ユー | Exactly like you |
| CD5-3、CD-1. | ダイナ | Dinah |
| CD5-4、CD-2. | タイガー・ラグ | Tiger rag |
ここからCDは5枚目、そして「ダイナ」と「タイガー・ラグ」は”The chronogical 1930-31”(Classics 547)にも収録されている。
[インディアン・クレイドル・ソング]
大和氏も、余り知られていない曲を取り上げたのは、ルイの好みであろうかと疑問に思っている様子である。ルイのヴォーカルのバックを飾るアディソンのギターが軽妙な味を出す。また歌の前にソロを取るキャスト―ル・マッコードのTsもコールマン・ホーキンス風のよい味を出していると大和氏は評している。
[イグザクトリー・ライク・ユー]
冒頭からルイのミュートは、抜群の歌心を示し、ヴォーカルも味が出てきていると大和氏は書くが、僕はルイのTp及びヴォーカルは1929年の「捧げるは愛のみ」辺りから抜群の味わいがあると思っている。
[ダイナ]
この曲は、昔日本でもディック・ミネの歌でヒットした曲。僕の父親もよく口ずさんでいたので知っている。
ここでは、オーケストラのリフをバックにラスト3コーラスをそれぞれに工夫を凝らしたフレイズを駆使して吹き分けるルイのソロが圧巻である。また歌の前に出るマッコードのTsソロは、20年代半ばのホーキンスを思わせる。歌の後に出るヘンリー・ヒックスのTbソロも好演である。
[タイガー・ラグ]
この曲に対しては、「当時のヒット曲だが、いわゆる高音ヒットを放つルイのテクニックのすごさをひけらかすための演出がなされた曲」と大和氏は述べる。後半の無意味な高音連発をトレード・マークとする、ルイにとっては泥沼の深みにはまったような録音が次第に多くなり、マンネリ化の時期を迎えたことを意味すると手厳しい。だがそういった中にもいくつかの注目すべき作品を残したことも事実であり、そういった録音ではルイの実力をまざまざと見せつけている。
なお、ロイ・エルドリッジはちょうどこういう時期のルイのテクニックやトーン、そして数々のアイディアに示唆を受け、スイング時代最高のトランぺッターへの道へと突き進んでいったと大和氏は付け加えている。

大恐慌の影響が深刻になり始めたこの時代、なぜルイの録音は減らなかったのであろうか?やはり売れていたのであろうか?もしかするとこのような時代を背景にしてルイは、売れる音楽を演らなくては…と思い詰めていたのかもしれない。
さてここからはルイ・アームストロングの1930年の後半、カリフォルニア時代となる。まず右はクロノジカル1930-31のCDに掲載されているルイの写真。このCDに掲載されているということは、この時期の写真のように思える。1901年生まれのルイはこの時29歳という男盛り、写真下部に”Just a gigolo”という文字が見える。”Just a gigolo”は翌1931年3月に吹き込んだ曲なので、31年の可能性が大きい。まぁ、この時期のルイは怖いもの知らずという感じだったのだろうと思う。
ともかくルイはカリフォルニアで、フランク・セバスチャンの経営する“ニュー・コットン・クラブ”に7月からソロイストとして出演した。当時このクラブに専属出演していたレオン・エルキンスのバンド(30年秋からレス・ハイトが率いる)と共演したが、このバンドはスティール・ギターやチューバの入ったジャズ的要素の希薄なローカル・バンドといってよかった。ただ、その中には注目すべき存在として、後年スター・ソロイストとなるローレンス・ブラウン(Tb)やライオネル・ハンプトン(Vib、Dr)が在団していたのである。

| Trumpet & Vocal | … | ルイ・アームストロング | Louis Armstrong | |||
| Trumpet & Condactor | … | レオン・エルキンス | Leon Elkins | |||
| Trombone | … | ローレンス・ブラウン | Lawrence Brown | |||
| Alto sax | … | レオン・ヘリフォード | Leon Herriford | 、 | ウィリー・スターク | Willie Stark |
| Tenor sax | … | ウィリアム・フランツ | William Franz | |||
| Piano | … | L.Z.クーパー | L.Z.Cooper | or | ハーヴェイ・ブルックス | Harvey Brooks |
| Banjo & Steel Guitar | … | シール・バーク | Ceele Burke | |||
| Tuba | … | レジー・ジョーンズ | Reggie Jones | |||
| Drums & Vibraphone | … | ライオネル・ハンプトン | Lionel Hampton |
| CD5-5、CD-3. | アイム・ディン・ドン・ダディ | I'm ding dong daddy |
| CD5-6、CD-4. | アイム・イン・ザ・マーケット・フォー・ユー | I'm in the market for you |
「ベニー・グッドマンの録音などでは「張り切りおやじ」と邦題がついている、当時のルイの傑作の一つに数えられるナンバー。最初のコーラスに出るTbはもちろんローレンス・ブラウン。ルイはヴォーカルの途中で「わしゃ歌詞を忘れたよ」と堂々と言い放ち、スキャットに入る演出を試みている。歌の後のテナー・ソロはタンギングを用いた古めかしいスタイルでどうしようもないが、それだけにルイのソロの素晴らしさが映える。このソロはミュージシャンの間で評判になったルイのソロの一つで、力強く、しかも淀みなく歌心があふれ出た名ソロである。
イギリスの自身ピアニストでもあり評論家でもあるブライアン・プリーストリー氏はその著『ジャズ・レコード全歴史』において、ディジー・ガレスピーの「ソルト・ピーナッツ」のメロディーは、ラッキー・ミリンダ楽団の「リトル・ジョン・スペシャル」として使われていたものだが、その元は、この「ディン・ドン・ダディ」でのルイのフレーズに基づいている。「ディン・ドン・ダディ」のブレイクのタイミングを反転させた3連符によって続けられている」と指摘している。確かに似ている感じはするが、そう言われて聴けばである。
一方何につけ手厳しいガンサー・シュラー氏は、「ルイの後15年間に登場したいずれのTp奏者も『ディン・ドン・ダディ』その他の曲のルイの奏する「本物の音」と深みを持ちえなかった。さらにこの曲で聴かれるルイのスキャット唱法の素晴らしさに関しては言わずもがなである。ただこの曲は、ルイが演奏している個所しか聴くところがない代物であるが」と、ともかくルイは素晴らしいことを認めている。シュラーさん、ローレンス・ブラウンもダメなの?
[アイム・イン・ザ・マーケット・フォー・ユー]
大和氏よれば、30年に作られた映画の主題歌であり、甘いメロディーを持ったポピュラー・ソングで、ここではルイのソロより、ヴォーカルの後に出るブラウンのTbソロが聴きものとなっているという。確かにブラウンのTbソロは短いが優しい音色で彼の特徴がよく表れた素晴らしいもの。続くギター・ソロは余りスティール・ギターの特徴であるスライド・プレイを多用していないが、いかにもそれらしい響きも聴かれる。その後のルイのオープンによるソロも歌心溢れて素晴らしいと思う。

7月21日と同じ。
| CD5-7、CD-5. | コンフェッシン | (I'm)confessin’ (that I love you ) |
| CD5-8、CD-6. | 今宵ひととき | If I could be with you one hours tonaight |
次の録音は約1か月後8月19日に行われた。この録音に関して大和明氏は、2曲ともスロー・テンポのノスタルジックな演奏で、当時の不況時代を反映しているとみられると書いている。不況だと、元気のよい闊達な曲よりゆったりとした昔を懐かしむような曲が好まれるということであろうか?
[コンフェッシン]
スティール・ギターによるイントロで、ムード満点の演出が施されている。ルイの歌のバックに、流れる甘美なサックス・ソリとスティール・ギターの響きがいかにもこのバンドらしいサウンドを奏でるが、やはりスティール・ギターはちょっと?と思う。それに対してブラウンとルイのソロはさすがに筋が通っている。しかしテナー・ソロは陳腐でいただけない。
[今宵ひととき]
全体的にセンチメンタルなムードが横溢しているが、ルイのソロは甘さに寄りかからないバラード表現で迫ってくるとは、大和氏。ヴォーカルの後のTbソロもブラウンらしくて良い。

| Trumpet & Vocal | … | ルイ・アームストロング | Louis Armstrong | |||
| Trumpet | … | ジョージ・オレンドルフ | George Orendorff | 、 | ハロルド・スコット | Harold Scott |
| Trombone | … | ルーサー・グレイヴン | Luther Graven | |||
| Alto , Baritone sax & conduct | … | レス・ハイト | Les Hite | |||
| Alto sax | … | マーヴィン・ジョンソン | Marvin Johnson | |||
| Clarinet & Tenor sax | … | チャーリー・ジョーンズ | Charlie Jones | |||
| Piano | … | ヘンリー・プリンス | Henry Prince | |||
| Banjo & Guitar | … | ビル・パーキンス | Bill Perkins | |||
| Bass & Tuba | … | ジョー・ベイリー | Joe Bailey | |||
| Drums & Vibraphone | … | ライオネル・ハンプトン | Lionel Hampton |
| CD5-9、CD-7. | 身も心も | Body and soul |
前録音から2か月弱一体何があったのだろう?リーダーが変わり、メンバーが一新されている。このメンバーの方がルイのバックにはふさわしいジャズ的センスを持ったバンドに変貌している。大和明氏が監修のCD解説では、前録音までのレオン・エルキンス率いるバンド名を”Louis Armstrong and his NEW Sebastian cotton club orchestra”とし、このレス・ハイト率いる新しいバンドを”Louis Armstrong and his Sebastian NEW cotton club orchestra”と”NEW”の位置を変えている。但しThe Chronogicalでは、どちらも”Louis Armstrong and his Sebastian NEW cotton club orchestra”と表記している。
さらに上記のパーソネルはCD解説のもので、そこではジョージ・オレンドルフ、ハロルド・スコット、ルーサー・グレイヴンの3人がTbとなっているが、The Chronogicalではオレンドルフとハロルド・スコットはTpでルーサーだけがTbとなっている。音を聴いてもこれはThe Chronogicalが正しいように思う。
ともかく新しくリーダーになったのは、当時ロスでは一応名の知られていたアルト・サックス奏者のレス・ハイトで、彼は、スティール・ギターやチューバのリズムを排し、メンバーも充実させた。残念ながらローレンス・ブラウンは去ったが、ハンプトンは残りこれまで通りに歯切れのよいリズムを繰り出している。
このバンドでの初録音は、後にジャズ・プレイヤーなら一度は必ず演ると言われる「身も心も」で、ルイはミュートで歌うがごとき暖かいソロと心の通ったヴォーカルで、いかにも人間味あふれるルイの人柄がにじみ出た仕上がりとなっているとは大和氏。

10月9日と同じ。
| CD5-10、CD-8. | メモリーズ・オブ・ユー | Memories of you |
| CD5-11、CD-9. | ユーアー・ラッキー・トゥ・ミー | You're lucky to me |
[メモリーズ・オブ・ユー
大和氏は次のように解説している。「この曲は、ライオネル・ハンプトンにとって思い出深い録音となった。彼はこれまでのも時々このレス・ハイト楽団でヴァイブを手にしていたが、たまたまこの時スタジオの隅で遊びがてらヴァイブを叩いていたところ、それに目を付けたルイが演奏に使うように勧めたので、ここに初めてヴァイブ奏者としてのハンプトンの録音が実現したのである。イントロからハンプは単なる効果音を超えた実に雰囲気のある美しいサウンドで、夢見るようなこの曲のムードを設定している。」
この曲は後に、ハンプトンが加わったベニー・グッドマンの重要な曲となる。BGはこの演奏を知っていて自己のナンバーとして取り入れたのかもしれない。
[ユーアー・ラッキー・トゥ・ミー]
ルイの歌の後に珍しいレス・ハイトのバリトン・ソロを聴くことができる。ラストのルイのソロは高音域での盛り上がりを狙ったもの。なお、この日に録音した2曲とも多くのディスコグラフィーには別テイクがあるように記載されているが、おそらくオリジナル・テイクの回転数を速めたもので、同じテイクではないかという。

10月9、16日と同じ。
| CD5-12、CD-10. | スィートハーツ・オン・パレード | Sweethearts on parade |
| CD5-13、CD-11. | ユーアー・ドライヴィング・ミー・クレイジー | You're driving me crazy |
| CD5-14. | ユーアー・ドライヴィング・ミー・クレイジー | You're driving me crazy |
| CD5-15、CD-12. | 南京豆売り | The peanut vendor |
約1か月半後に行われた1930年最後の録音。この日は3曲録音されたが、その1曲は2つのテイクが発売されたという。
[スィートハーツ・オン・パレード]
オーケーによるビッグ・バンド時代の演奏の中で、<シャイン>、<アイム・ディン・ドン・ダディ>などと並ぶ最良の演奏の一つであろうと大和氏は述べる。ここではルイの歌も味わいがあり、その前のミュート・ソロでの人の心をそそるような優しい歌心、そして歌の後に出るトランペット・ソロにおける創造に富んだ展開の見事さといい、この時期の名演の一つといえよう。
[ユーアー・ドライヴィング・ミー・クレイジー]
2つのテイクが並んでいるが、CD5-14は稀少視されていたもので、心持ちCD5-13よりもテンポが速い。両テイクにソロの構成に違いはないが、ヴァリエイションの端々に違いが見られる。
語りでやり取りをしているのは、ルイとハンプトンである。
[南京豆売り]
後にスタン・ケントン楽団の十八番となった曲。この年欧米のボールルームなどで、これまでにない独特のノンビリしたルンバによるラテン・ナンバーとして、その目新しさが大衆に大いに受けたという。全体的にはコマーシャルな狙いを持った演奏だが、ここでは中心となっているルイのヴォーカルが結構ジャズ的センスを発揮している。